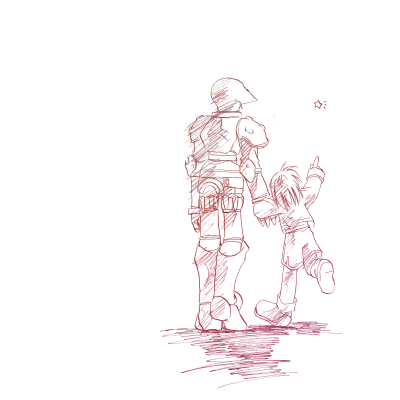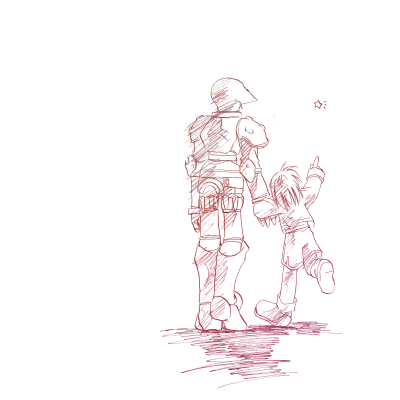正直に云ってしまおう。
ああは云ったものの、自分が、そんなに強い人間だとは思ってない。
ただ、強く在りたいとは思う。
ただ、望む未来を引き寄せたいと思う。
それは自分が動かなければ得られないと思うから、動く。がんばる。
がんばって、がんばって――
やっと、それに手が届いたと思ったのに。
「ゼルフィルド!!」
叫んで。跳ね起きた。
「……あれ?」
見慣れた部屋だった。ギブソンとミモザの屋敷の一室、たちに割り当てられた部屋。
けれど、同室の数人の姿はなかった。
薄手のカーテンだけが閉められた窓から見える景色は、夜空。
数度、またたきする。
じんわりと熱を訴えるまぶたを、冷え切った手のひらを押し当てて鎮めようとして――ふと。
固く固く、握りしめたままの指に、ようやく気づく。
部屋に灯りはついていない。
窓を抜けてどうにか届く月光が、うっすら照らす暗がりのなか、の手に握られたそれは、ほのかな光を発していた。
「……ゼルフィルド……」
あたたかな光。やわらかな波動。
強張っていた身体の力が少し抜けるのと同時、思い出したくもない光景を思い出し、身震いした。
あのとき、の前に落ちてきた光る欠片。これがそうだった。
無我夢中で手にとったけれど、果たしてこれは何なのだろうか――同じ機械兵士であるレオルドなら、何か教えてくれるだろうか。
誰かが、泥にまみれた衣服から着替えさせてくれたんだろう、夜着。その上にショールを羽織って、は部屋から滑り出た。
レオルド、どこにいるかな――そう思いながら、頭でなぞるのはゼルフィルドの行動。
機械兵士は睡眠を必要としないし、その自重の関係もあるし、たしかあまり一般家屋の中には入らないはずだった。
だとしたら、庭だろう。
月光でもたしか、充電は(太陽光には及ばないけど)出来るとたしか、ゼルフィルドから聞いた覚えがあったから。
やわらかな、光るかけらを手に持ったまま、向かう先は――庭。
「……コレハ、こあ、デス」
「コア?」
予想通り庭にいたレオルドに声をかけたら、彼はまず、一瞬、がきょっと奇妙な音をたてて停止してた。
もしかして、驚いたんだろうか?
復帰するのを待ったが、とりあえず解を得ようと見せた光る欠片を見て、レオルドは、今のような答えを寄越したのである。
おうむ返しにつぶやいたへ、「ハイ」と、レオルドは頷く。
それを耳にしながら、夜気の寒さに少々身体を震わせたら、何気に風上に移動してくれさえしながら、
「我々ニモ、アナタ方ト同ジヨウニ、心臓トモ云エル中枢ガアリマス。ソレガこあデス」
「……じゃあ、これって」、この暖かな鼓動は。「ゼルフィルドの心臓なんだ……」
「ハイ。彼ノコレマデノでーたガ、ソノナカニハ詰マッテイルノデショウ」
戦い方や、記憶や。
ルヴァイドやたちと過ごした日々も。
この中に?
持ち上げて月光に透かすと、それは、きらりきらりと優しく光る。
これがゼルフィルドの心臓だったのだ。
――大きくて、強くて、優しい、漆黒の機械兵士。彼の。
「そっか……」
……そうかあ……
涙なんてもう枯れたと思っていたのに、また、雫が頬を伝う。
レオルドが、手のひらをに伸ばそうとして――やめた。
「レオルド?」
何がしたいのかつかめず、疑問符乗せて名を呼ぶと、
「申シ訳アリマセン」と、唐突な謝罪。「私ノ性能デハ、微妙ナちから加減ガ出来ナイノデ……」
「……そうなの?」
「ハイ。マダ経験ガ足リマセンカラ」
「……もしかして、なでてくれようとしてた?」
「恥ズカシナガラ……」
「……、あははっ」
意図せぬまま零れた笑いに、は、驚きはしなかった。ただ、レオルドの気遣いが嬉しかった。
「……ねえ、レオルド」
ふと思いついて、は笑みを引っ込める。そうして、真正面からレオルドに向かい合った。
「このコア使って……ゼルフィルドを生き返らせたりは……?」
キイィ、と、音がした。
唐突な質問に、レオルドの思考ルーチンが急回転しているらしい。
そうして、待つことしばし。答えがはじき出される。
「可能デス。ガ、不可能デス」
前後で矛盾しきったそのことばに、の目は丸くなる。
一瞬意味をつかみ損ねたことを判ってくれたのか、レオルドは、少し間を置いてから付け加えてくれた。
「知識、経験、記憶ハ、タシカニ、ソノ中ニスベテ記録サレテイルデショウ」
こあノ型ニ合ウぼでぃサエ都合出来レバ、機械兵士トイウ形ニハ戻セマス。
「デスガ、ぜるふぃるどガぜるふぃるどタル何カハ、でーたトイウ形デハ保存出来ナイモノデハナイデショウカ」
「……こころ……」
「アナタ方ガ、ソウ呼ブモノハ、でーたトシテ解明デキルモノデハアリマセンカラ」
「――――」
なんだか、驚いてしまった。
殆ど不可能だろうなと思っていた、の気持ちを読まれたんじゃないかとさえ、思ってしまった。
目をしばたかせているを、レオルドは、少し首を傾げて静かに見ている。
それはたちのような見え方なのか判らないけれど、その視線は、静かにを包んでいる。――ゼルフィルドと同じように。
「……そうだね」
じゃあ、さ。頷いて、つづけた。
「ゼルフィルドは、還れるかな」
「ハイ。キット」
間髪いれずに、レオルドは云う。
「……そうだね」
きっといつか、今のあたしじゃないあたしと、出逢うことがあるかもしれないね。
事実はそうでないとしても、せめて、そう信じたかった。
さきほどよりずっと穏やかな気持ちになって、は、ゆっくりと口の端を持ち上げる。
「ありがとう、レオルド」
「イ、イイエ、殿ノ気持チガオ強イカラコソ――」
「ところでさ」
しどもどになる機械兵士をかわいいなと思いながら、レオルドの目の前に、ゼルフィルドのコアを掲げて見せた。
「これさ、読めたりする?」
「エ?」
「……ゼルフィルドの経験とか、記憶とか、レオルド、受け取れる?」
「ソレハ……」
しばらくの間。
「……ハイ」
「良かった」
にこりと笑ってみせると、レオルドの駆動音が、少しきしんだ。
「良イノデスカ? 貴方ノ家族ノ記憶ヲ、私ガ暴クコトニナリマスヨ」
「いいの」
きっと、ルヴァイドとイオスもそう思ってくれるだろうと考えながら、もう一度笑う。
「ゼルフィルドが積み重ねてきた経験、きっとレオルドを強くしてくれる。これからまだ戦いは続くだろうし……それに、ゼルフィルドの技術や経験、このまま腐らせたくないもん」
「腐ルモノナノデスカ」
「インプットしないでいーからね。比喩よ、比喩」
真面目に応じるレオルドに一応ツッコんで、それから、コアを差し出した。
「……」
少し躊躇うような間を置いて、レオルドの手が、慎重に、コアをから取り上げる。
ボディのどこぞから、端子が数本伸びてきて、コアに接続された。
――そうして、かすかな読み取り音。
データを読み取り、解析を続けながら、その片隅――まだ余裕のある思考回路の一部でもって、レオルドは考える。
が良いというのだから、このゼルフィルドの経験と知識を、読み取らせてもらっている、この現実にあたってのことだ。
……そう。読み取っている。
レオルドは、ゼルフィルドが、このコアに蓄積してきたデータをすべて、読み取っていた。
だから考えるのだ。
それを、果たして、伝えるべきだろうかと。
それは、あの場でゼルフィルドが発さなかった、ことばの群れだった。
彼らの機体には、最終手段として敵を殲滅するための、自爆装置がついているのは、ゼルフィルドで証明されたとおり。
そうしてそれはデータ上、召喚師の唱える最上級の術に等しい威力である。
だがけして、メルギトスを一撃で追い込むまでの威力ではないことをレオルドは――ゼルフィルドもまた、判っていた。そのはずだった。
万が一、億が一。
人々が奇跡と呼ぶものでも起こらない限り。いや、起こったとしても――
それでも。
そういうことを判っていて、ゼルフィルドが、その命を賭した理由を。
ことばという形で、伝えられるのだろうかと。
レオルドは、思考する。
「殿」
「はい、お疲れ」
しばらくして、そう呼びかけられたとき、コアを返されるのだと思って手を差し出したら。
「――コレヲ」
まるでサーチライトのように、レオルドの双眸が光を発した。
ただしにではなく、すぐ傍に佇む一本の木に向けて。
大人がふたりで抱え込めるほどの太さの幹に、ライトは細かな色の粒子を躍らせながら、何かの影を――
「……!!」
笑っていた。みんなが。
これはいつの光景? 覚えがあるような、ないような、もう随分と昔のような。
そうだ、たしか。
……記憶の一端を刺激され、はそれを思い出す。
珍しく天気の良かった日、駄々こねて一斉休暇としゃれこんだときの。それは、光景だった。
緑あふれる丘。珍しく私服のルヴァイドとイオス。それから、旅団のみんな。ゼスファ。シルヴァ。ウィル。
笑っている。みんなが。
笑っている。
この視線の主に呼びかけているのか、大きく手を振り回した形で。が。
「ぜるふぃるどノ、一番鮮明ナ記憶デシタ……デスガ、記録日事態ハ古イモノデス。数ヶ月前ノ――」
笑っていた。 みんなが。
「最後ニ強ク、思ッタモノダッタノデショウ」
ルヴァイドが、イオスが、兵のみんなが。が。――ゼルフィルドが、きっと。
……笑っていた。
緑あふれる丘。光に満ちた世界。
一緒にいた、優しい人たち。大好きな家族。
笑っていた。
笑っていて。
……これまでも。これからは、
それは、遺されたことば。
笑った彼らが。
まえへ
さきへ
――持っていけ、!
何も云わぬまま行った、漆黒の背中が。
だからそれでも。
笑っていた。
笑っていて。
――これからは。これからも。もう。
「――……っ」
限界だった。あとからあとから、水滴が頬をつたって滴り落ちる。
ぼやけた視界のなかで、けれど不思議に、レオルドの映し出したその光景ははっきりと見えた。
それがまた、涙腺を刺激しまくってくれて、仕様がない。
肩が震える。
寒さか。
重みか。
おそらく両者。
そこに、固い金属の手がそっと添えられる。
「ばか……っ」
夜気で、金属は殆ど熱を奪われるはずだった。
けれどそれは、ひどく暖かくて。
甘えてしまいたくなる気持ちを、寄りかかってしまいたくなる心を、ぎりぎりで押し込めて。
「……ばか……!!」
ただ、そう繰り返しつづけた。
遠ざかった背中。漆黒の背中、黒い鎧。
そして、ずしりと重みを増した、手の中の輝きへ向かって。